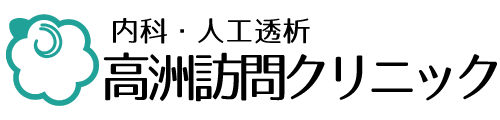臨床工学技士の羽田です。
第70回日本透析医学会(2025年6月27日~29日、大阪府)で発表をしてきました。演題は、「保存的腎臓療法から血液透析療法を選択した患者の変化の要因」です。
腎機能が悪化し、自分の腎臓では体の環境が維持できなくなったとき、腎臓の代わりをする治療(腎代替療法)が必要になります。今までは、透析療法(血液透析と腹膜透析)と、腎移植(献腎移植と生体腎移植)が提案されてきましたが、近年の高齢化に伴い、症状の緩和、心理的社会的支援を重視した保存的腎臓療法(Conservative Kidney Management:CKM)が選択肢として加わるようになりました。
過日、他院の医師より、「CKMを選択していた方が、日常生活を自力で行うことが厳しくなった」という入院相談がありました。その方は、入院後に血液透析を選択し、退院後も継続して通院しています。このような事例は近年増加しており、「この心境の変化の要因は何だろう」と、情報を整理し、まとめ、発表しました。
発表したセッションでは医師の参加が多く、質問も活発でしたので、やはりCKMという治療選択はホットなトピックスなのだろうなと思いました。また会場では、様々な視点からの発表や質問があり、たいへん勉強になりました。
CKMを選択するまでの過程には、人それぞれの考え方や家族の気持ちなど、様々な背景や生き様があり、今後の治療方針を決定するにも、個々人にあった話し合い(SDM)が重要と思います。
高齢化が進む昨今、このような方々がさらに増加していくことが想像できます。透析導入の是非に関わらず、患者や家族に寄り添いながら、それぞれに合った治療やケアができるようにしていきたいと、強く思っています。